透明水彩のための水張り時間|失敗しないコツは焦らず30分!
こんにちは、NORi です。
たっぷり水を使って描く水彩画には欠かせないと言われる『水張り』ですが、使う紙の厚さや塗り方によっては実は必要ありません。300g/cm2くらいまでの厚さの紙では、丁寧に水張りをしたほうがその後の作品の仕上がりが綺麗です。
そこで今回は、失敗談なども交えて、水張りのコツや、やり方(霧吹きバージョン)などをご紹介してみようと思います。
 NORi
NORi
- 透明水彩のための水張り時間|そもそも『水張り』とは。
- 透明水彩のための水張り時間|はじめての水張りのやり方。
- 透明水彩のための水張り時間|水張り失敗例① -『水張りしたのに、紙が波打つ』
- 透明水彩のための水張り時間|水張り失敗例② -『水張りしたら、色が塗れない???』
- 透明水彩のための水張り時間|水張りの準備 ~霧吹き版~
- 透明水彩のための水張り時間|水張り実践編 ~霧吹き版~
- 1. 裁断した紙を広げる。
- 2. 【 片面 15分 – 霧吹きスタート 】 紙に水をかける。
- 3. 【 5 分霧吹き経過 】紙に水が吸収されていく。
- 4. 【 10 分霧吹き経過 】水に浸しているイメージで、ひたすら水分補給。
- 5. 【 片面 15 分間霧吹き完了 】 15 分間水に浸し続ける。
- 6. 【 ひっくり返す 】紙に傷がつかないように注意します。
- 7. 【 裏側 15 分 – 霧吹きスタート 】再び、霧吹きスタート。
- 8. 【 裏側 15 分 – 霧吹き完了 】紙をパネルに固定する準備。
- 9. 【 水張りテープを貼る 】紙をパネルに固定。
- 10. 【対辺を留めていく】向かい合った辺を固定。
- 11. 【 乾燥 】直射日光を当てずに日影で自然乾燥。
- 透明水彩のための水張り時間|まとめ
透明水彩のための水張り時間|そもそも『水張り』とは。

水彩紙に絵の具が溜まる様子 by NORi
水彩画では、
絵の具を水で溶く際に
たっぷり水を使うことがあります。
画用紙に色を塗ると
絵の具が水溜りのように溜まったり、
紙自体がふやけて
大きく波打つことがあります。
このようなことが
絵を描いている途中で起こると、
思ったように
色を塗ることができなくなります。
紙がうねってしまったり、
絵の具が溜まったところだけ
画用紙が凸凹してしまうと、
絵の具が勝手に
流れて行ってしまうからです。
そこで、
絵を描く前にあらかじめ
紙を水で十分ふやけさせて、
これ以上
紙が伸びないところまでふやけさせて、
その状態で紙を板に固定してしまう方法を
『水張り』といいます。
強力なテープなどを使って
紙が完全に伸び切った状態で
しっかりと板などに固定するので、
そのまま乾かすことで
ぴーんと張った紙の状態が作れます。
水張りした後の乾いた
ぴーんと張った綺麗な紙に
水をたっぷり使って絵の具を垂らしても
紙はうねったり
凸凹することがなく、
とても快適な環境で
絵が描けるというわけです。
素晴らしいですね!
■ 水張りテープ。

愛用の水張りテープ by NORi
上の写真の右側のテープが、
紙を綺麗に板に固定するための
『水張りテープ』です。
とても強力なテープで、
湿気で糊が溶け出して
テープ自体がくっついて
取れなくなってしまうことがあります。
そのため、
ビニール袋に入れて保管します。
この強力なテープを使って
水張りをした紙は、
水をたっぷり使った絵の具で色を塗っても
紙はそれ以上ふやけませんから
ピーンと張ったままで
作品も綺麗に仕上がります。
特別に厚い水彩紙を使って絵を描く場合には
水張りをしなくても大丈夫な時がありますが、
300g/cm2 程度の厚さの紙までは
水張りをしておくと安心かと思います。
■ 水張りの時間について。

水張りは
充分に紙に吸水させて
伸び切った状態にすることが大切ですが、
どのくらいの時間
水に浸せば
紙は完全に伸び切ったと言えるでしょうか。
それは、
紙の種類(メーカー)や
紙の厚さによっても異なります。
紙の原材料や製法が違うことで
吸水性も変わってきます。
水張りをする前に
紙の吸水性をあらかじめ知っておくと
安心です。
例えば、
比較的ゆっくり水を吸収する
アルシュという紙(300g/cm2の厚さ)の場合、
水に紙を浮かべた後
15 分 ~ 20 分水に浸しておくと、
紙が水で充分にふやけて
ほぼ完全に紙が伸び切るという
実験結果があります。
そこで私は
片面 15 分以上、浸水することにしました。
最短でも両面で 30 分です。
紙は完全に伸び切って、
これで
水張りに失敗することはなくなりました。
透明水彩のための水張り時間|はじめての水張りのやり方。

紙を水に浸す方法としては、
洗面台やお風呂などに水を張って
紙を浸すのが簡単です。
紙を水に浸す際、
紙はすぐには
水の中に沈みません。
初めのうちは
紙が丸まっていたり、
紙が水に浸からずに浮いてしまいます。
そうした状態では
充分に吸水することができませんから、
紙はなかなか沈みません。
でも、それで大丈夫です。
最初は
水に触れている紙の下の面だけが
吸水しているということになりますが、
徐々に水が全体に浸透していき
紙も平らになっていきます。
片面ずつ 15 分
吸水させれば
両面がすっかり伸び切ります。
紙が伸び切ったら
水張りテープを使って紙を板に固定します。
具体的な方法は
このページの下の方で解説しております。
写真を載せておりますので、
紙が伸びていく様子などが
分かりやすいと思います。
洗面台などに紙を浸せない場合の
霧吹きで吸水させる方法でご紹介しています。
■ 水張りを成功させるコツ。

以上をまとめますと、
水張りを成功させるコツは
これ以上ふやけなくなるまで
充分紙に吸水させることです。
そのために必要なのは
吸水させるための十分な時間です。
片面ずつ 15 分
吸水させれば
両面がすっかり伸び切りますので
それで大丈夫です。
まずは紙を水に浮かせて 15 分。
ひっくり返してさらに 15 分です。
これが終わると、
紙は完全に吸水して
水に浮いた状態ではなく
水の中へと沈んでいます。
放っておくだけですが、
これで失敗することはなくなりました。
実は
この方法を知る前のわたしは、
水張りに失敗して
恥ずかしい思いをしたことがありました。
そのときのことを
少しお話してみようと思います。
透明水彩のための水張り時間|水張り失敗例① -『水張りしたのに、紙が波打つ』

絵をはじめて 2 年が過ぎた頃でした。
私は少し大きな絵に挑戦しようと思い、
F15号 (65.2 × 53.0 cm) という
サイズの紙(シート)を水張りしました。
このような大きさの紙を水張りするのが
初めてだった私は、
うまく水張りができず
失敗してしまった様子。
きちんと水張りしたつもりで
しっかり紙も乾かしておいたのですが、
その紙に
絵の具で色を塗っているうちに、
徐々に紙が
波打ってくるが分かりました。
そのまま様子を見ていると、
紙が乾いても
紙の凹凸はそのまま
少し残ってしまいました。
■ そして出品。
紙の凸凹は多少残ってはいましたが、
額に入れれば
それほど気にならなくなりました。
その頃のわたしは、
水張りに必要な時間というものを
知りませんでした。
自分の描いた作品にも
それほど大きな影響はないと思い、
ある小さな美術展覧会に
そのまま出品をしました。
展覧会の初日、
会場に足を運んでみたところ、
私の絵の前で立ち止まって
作品を見て下さっている男の方がいました。
私の絵も
観てくださる方がいるんだなぁと思い、
「絵を観て頂きまして、
ありがとうございます。」
と声をかけました。
すると、
その方はニコリとほほ笑んで
挨拶をしてくださいました。
その方は
審査員の画家の先生の一人でした。
■ 先生の言葉。

その先生は、
私の絵を眺めながら
こうおっしゃいました。
『 色が良いね。
透明水彩らしい繊細な色合いが
よく表現できていると思うよ。
もう少し立体感を引き立てるような
工夫が出来ると
もっと良くなるね。
構図も良いと思うよ。
空白の処理に
もう少し力を入れたらいいかな。
ただね・・・ 』
■ 目立つのは、基本の部分。
先生は続けて
こうおっしゃいました。
『 水張り、失敗したでしょ。』
わたしはドキッとしました。
『 紙がうねっているもんねぇ。
もったいないねぇ。
こういう、
基本的なところは
きちんとしておかないといけないねぇ。』
んー、やっぱり!!!
なぜ、
水張りをし直さなかったのだろうと、
今更ながら私は
とても恥ずかしくなりました。
『 来年は期待しているからね。』
先生はニコッと笑顔を見せて
帰っていかれました。
この先生の笑顔が心に焼き付いて、
来年はきちんとした作品を
出品しようと心に刻んだのでした。
水張りの大切さを
心に刻んだ出来事でした。
透明水彩のための水張り時間|水張り失敗例② -『水張りしたら、色が塗れない???』
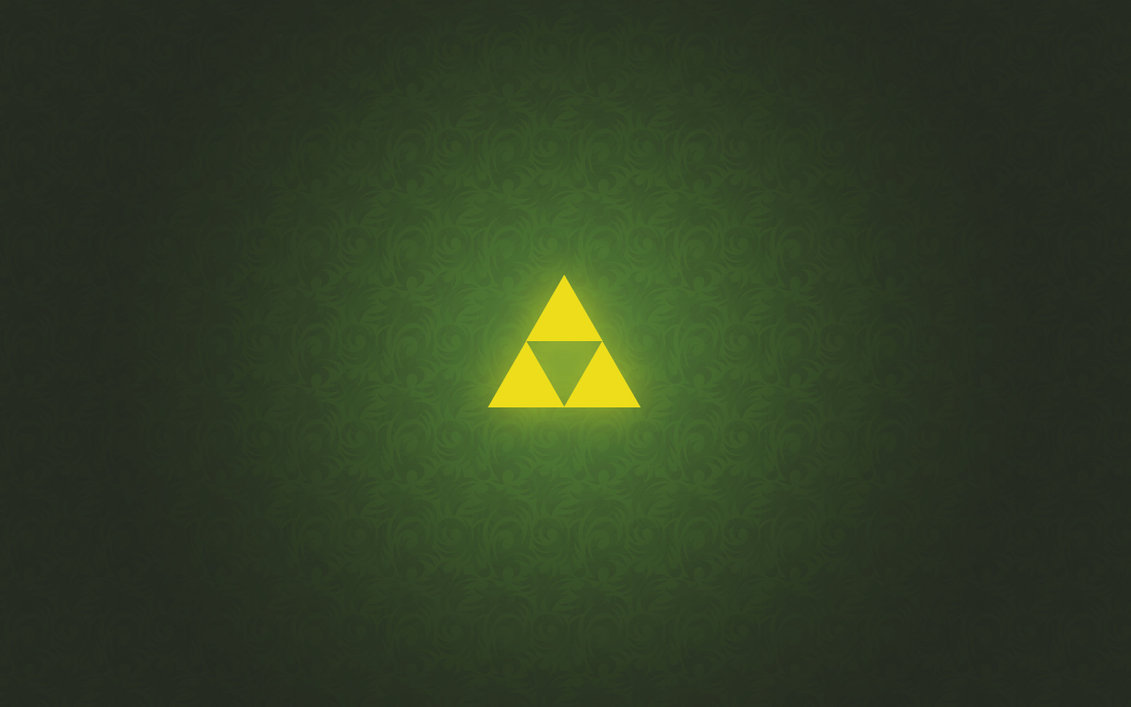
もう一つ水張りの盲点?といえるような
エピソードを書いてみます。
このようなこともあるのか!
と大変勉強になった出来事でした。
『 なんかおかしい。。。』
水張りを終えて
いよいよ紙に絵の具をのせて
と思ったら、
どうもおかしいのです。
紙に乗せた絵の具は
瞬時に紙に浸透してしまい、
紙はしっかり乾いているのですが
塗った場所以外の周辺の紙の部分にまで
絵の具の水分はどんどん広がっていきました。
ちょうど和紙に墨を落としたような
そんな具合でした。
この時も
使っていたのはアルシュ紙で、
本来は比較的よく水をはじき
ゆっくりと水が浸透していく紙なのです。
このようになってしまうと、
もうその紙では
絵は描けません。
■ 何が起こっているの?
実はこの一幕は、
自宅の洗面台で水張りをしてから
ようやく色を塗り始めたときのことでした。
水張りをするまえに裁断してあった
紙の切れ端が残っていたので、
その切れ端の紙に
試しに絵の具を乗せてみたところ、
しっかりと水をはじき、
その後ゆっくりと水が浸透する様子を
確認することができました。
切れ端の紙の状態は正常だったので、
水張りをして
画版に張り付けた紙の方が
おかしいことがわかりました。
■ 水の吸水性。

今回トラブルを起こした
画版に水張りをした紙は、
あまりにも吸水性が高い状態になっていました。
もしかしたら、
界面活性剤を主成分とした洗剤などが
紙に含まれてしまったのかな?
と思いました。
今回の水張りは、
洗面台のシンクに水をはって
水張りをしていました。
もしかしたら
なにか洗剤が残っていたかもしれない、
と思いました。
その後、
自宅のシンクを
念入りにお掃除してから、
もう一度、水張りに挑戦。
恐る恐る絵の具を垂らして
紙の具合をチェックしてみたところ、
無事にクリア!
正常に絵の具をはじいていました。
■ 水が命の水彩画。
このようなことは
失敗してはじめて気が付くことですが、
これは水張りの盲点かもしれませんね。
水張りの際には
きれいな場所できれいな水を使うことが
大切だということを
改めて確認できた出来事でした。
水彩画は
水が命の技法です。
画家さんの中には
水の種類にこだわって、
作品の制作には水道水すら使わない方も
いらっしゃいます。
水の違いで絵の具の発色が変わるのです。
繊細な色合いを追究することで
水彩画の美しさが際立つのですから
奥深い世界ですね。
透明水彩のための水張り時間|水張りの準備 ~霧吹き版~

紙が大きくて、
シンクなどに紙を浸すことができない場合は
どうすればよいでしょうか。
ここでは
紙が大きくて洗面台などで
水に浸すことが出来ない場合に
霧吹きを使って水張りを行う方法を
ご紹介してみようと思います。
以下の画像で
紙が水を吸収する様子もわかると思いますので、
シンクなどで水張りをする際の
紙の時間変化の参考にもなるかと思います。
まずは、
準備した道具は以下の通りです。
- 30 号サイズにカットした紙(アルシュ 300g/cm2 coldpress)
- 40 号サイズの木製パネル(ベニヤ板)
- 水張りテープ(湿気ないようにビニール袋に入れたまま保管)
- タイマー
- 霧吹き
- キッチンペーパー
透明水彩のための水張り時間|水張り実践編 ~霧吹き版~

上の《水張り失敗例②》で
水張りを行う場所を綺麗にしておくことと
水張りに使う水は綺麗な水を使う事を
お伝えしました。
もうひとつ注意しておくことは、
紙の表面に傷がつかないようにすることです。
透明水彩は
一度ついてしまった紙の傷も
消せないほどの透明度の高い技法です。
濡れた紙は傷がつきやすいので
紙は丁寧に扱うことが大切になります。
1. 裁断した紙を広げる。
 ※ 写真の紙は 30 号サイズ (90.9 × 72.7cm) の作品のために、のりしろとして 3cm( 1.5cm × 2 )ほど多めに取って 94 × 76cm に紙をカットしたものです。 紙は ARCHES というフランス製の紙です。 今回は、筒状に丸めた状態で売られているロール紙を購入して裁断しました。 写真の紙はロール紙を裁断したばかりの状態なので、まだ紙が丸まったままです。 重しとして厚い本(ビニール袋でカバー)で四つ角を抑えて紙を広げました。 |
2. 【 片面 15分 – 霧吹きスタート 】 紙に水をかける。
 ※ 霧吹きで全体にくまなく水を吹き付けていきます。 最初は紙が水を弾くので、紙の上に水たまりができます。 |
3. 【 5 分霧吹き経過 】紙に水が吸収されていく。
 ※ 少しずつ紙が水を吸い始めると、自然に紙も平らに広がっていきます。 紙の表面を眺めながら、水の潤いが消えてきた部分には途切れなく霧吹きで水を足していきます。 まだ紙の端っこは丸まっています。 |
4. 【 10 分霧吹き経過 】水に浸しているイメージで、ひたすら水分補給。
 ※ トータルで 10 分間、霧吹きで水分を補給した状態です。 紙がだいぶ平らに広がってきました。 重しはいらなくなりました。 |
5. 【 片面 15 分間霧吹き完了 】 15 分間水に浸し続ける。
 ※ 最後の 5 分も引き続き、紙の表面を横から眺めながら、常に水の膜が充分できている状態をキープするように霧吹きを続行します。 |
6. 【 ひっくり返す 】紙に傷がつかないように注意します。
 ※ ここまで 15 分間、水を充分吹き付けていましたが、裏側は乾いていることが分かります。 やはり裏側もしっかり水に浸さないといけないようです。 |
7. 【 裏側 15 分 – 霧吹きスタート 】再び、霧吹きスタート。
 ※ 再び、霧吹きで反対側の紙全体にも水を吹き付けていきます。 やはり最初は紙が水を弾くので、紙の上に水たまりができます。 |
 ※ こまめに霧吹きを繰り返します。 紙の表面が常に水の膜で覆われている状態を確認しながら、全体くまなく水分を補給します。 |
8. 【 裏側 15 分 – 霧吹き完了 】紙をパネルに固定する準備。
 ※ ここで、水張りテープを準備します。 木製パネル(ベニヤ板)の上に縦2本、横2本に並べてあるのが、はさみで切った水張りテープです(茶色のテープ4本)。 紙の上下左右を板にしっかり貼り付けて固定できるように、長めに切ってあります。 これから紙を木製パネルの上に張りつけるのですが、用意する木製パネルは紙よりも少し大きめのものが必要です。 今回は 30 号の紙なので、木製パネルは 40 号サイズのものを用意してあります。 |
 ※ 紙をひっくり返しながら、そっと木製パネルの中央にのせます。 最初は紙がパネルの中央にうまく乗らず、大きくずれて置いてしまったりするのですが、無理してズラさずに、一旦、そっと板から紙を浮かせて、紙を引きずらないようにやり直します。 紙に傷がついてしまうと、絵の具で塗ったときに傷が濃く滲んでしまい、絵の失敗につながります。 何度もやり直すのですが、どうしてもパネルから紙が少し出てしまって、何度も繰り返して、やっと中央に紙が乗りました。 少し紙の表面が乾いてきたので、もう一度、全体に霧吹きをしました。 |
9. 【 水張りテープを貼る 】紙をパネルに固定。
 ※ 水張りテープの内側(糊のついた面)は、水をつけると強力な糊がすぐに溶けだして、しっかり紙に張り付きます。 今回は、使い捨てのビニールシートを敷いて霧吹きをしていたので、余分な水分がビニールシートにたまっていました。 この水を使って、水張りテープを濡らしました。 水張りテープは水を付けたらすぐに使います。 |
 ※ 紙の端(のりしろ分) 1.5cm くらいを留めるつもりで、水張りテープが曲がらないようになるべくまっすぐに貼ります。 キッチンペーパーを四つ折りにして(または、ティッシュや使い捨てのタオルなどで)、上から軽く押すようにして余分な水分を取り除きながら、テープと紙とパネルを綺麗に密着させます。 |
       ※ 今回、水張りテープに水をつけるとき、紙の下に敷いていたビニール袋に残った水を使いました。 水張りテープの糊はかなり強力で、ビニール袋にも糊がついてベトベトになりました。 このビニール袋は使い捨てになります。 水張りテープに水を濡らすときは、掃除がしやすい洗面所でやるか、使い捨てのビニール袋を敷くなど、糊がついても困らない環境をしっかり整えてから水張り作業をすると安心です。 |
10. 【対辺を留めていく】向かい合った辺を固定。
   ※ 水張りテープを貼る順番は、対辺を固定するように留めていきます。 例えば、紙の上を留めたら、次は下を止めます。 次に、右を留めて、最後に左を留める、といった具合です。 大きなヨレを作らないためです。 |
11. 【 乾燥 】直射日光を当てずに日影で自然乾燥。
 ※ 四辺を水張りテープで固定して、完成です。 あとはこのまま自然乾燥させます。 ある程度乾いてくるまでは、水分が偏らないように平らなところに置いておきます。 直射日光に当てたりして急激に乾燥させると、紙が部分的に急激に縮み、テープが外れたり、紙が破れたりすることがあります。 乾く時間は紙の大きさによっても異なります。 30 号程度の大きさの場合には、完全に乾くまで、平らなところで丸一日(季節や天候によっては、念のため二日)は放置してから制作にとりかかるようにしています。 |
透明水彩のための水張り時間|まとめ
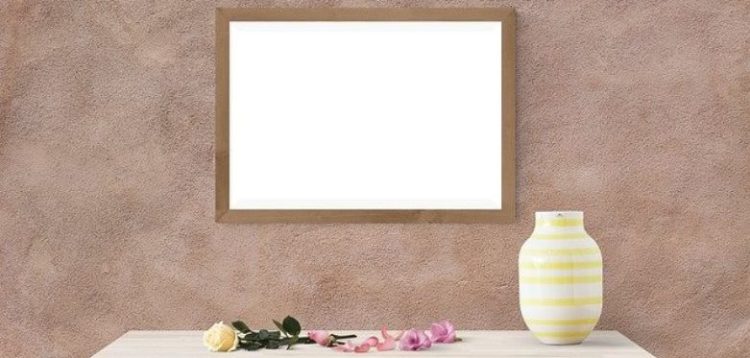
- 水張りは綺麗な場所で、綺麗な水を使って行います。
- 30 分の吸水時間を待てば紙はしっかり伸び切ります。。
- 紙を傷つけたり汚したりしないように丁寧な『水張り』作業を心がけることが作品の出来栄えをグッと上げてくれます。
特別に厚い紙でない限り、水張りはやはりしたほうが綺麗な作品に仕上がります。美しい作品づくりのためにも、水張りしないのはもったいないかもしれませんね。
 NORi
NORi
🔻関連記事


